
暗号資産(仮想通貨)は、国際的な金融市場や資産運用での活用も進んでいます。中でも、安定した価格を維持できるように設計されたステーブルコインは、その特徴を活かした新しい事例が増えています。
暗号資産市場の拡大や資産運用を始める人の増加で注目の集まるステーブルコインですが、メリットだけではなく注意点も存在します。
そこで今回は、ステーブルコインの特徴やメリット、注意点について解説していきます。
この記事を読めば、ステーブルコインの基本が理解でき、最新の暗号資産関連のニュースが理解しやすくなるでしょう。
株式会社リッカ
<<あわせて読みたい>>
【ブロックチェーンのトークンとは?】種類や違いをわかりやすく解説
ステーブルコインとは?
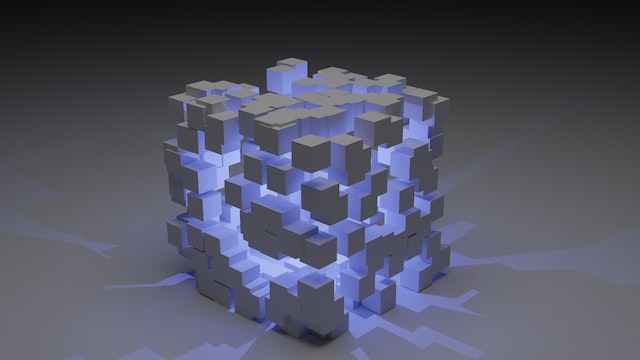
ステーブルコインとは、価格が安定するように設計された暗号資産(仮想通貨)です。
ビットコインを始めとする暗号資産は、市場の需給によって価格が決まるため、ボラティリティ(価格変動幅)が大きく、資産運用や決済手段としての活用が難しいというデメリットがあります。
一方、ステーブルコインの価格は安定するように設計されているので、ビットコインなどの暗号資産を利益確定のためにスワップしたり、世界中の人々とスムーズな送金や決済を行ったりする目的で活用されています。
ステーブルコインの価格が安定する仕組み
ステーブルコインは、資産を担保にしたり、プログラミングによって自動的に価格を調整したりすることで、取引価格を安定化させています。
ステーブルコインの価格を安定させる主な仕組みには、以下の4つがあります。
- 法定通貨担保型
- 暗号資産担保型
- コモディティ型
- アルゴリズム型(無担保型)
法定通貨担保型
法定通貨担保型は、米ドルや円などの法定通貨を担保にすることで価格を安定化させているステーブルコインです。
例えば、代表的なステーブルコインであるUSDT(Tether)やUSDC(USD Coin)などは、米ドルの価格に連動するように設計された法定通貨担保型であり、1USDTや1USDCは1ドルと同じ価格を維持するために、発行したステーブルコインと同等以上の米ドルや米国債などを保持しています。
暗号資産担保型
暗号資産担保型は、特定の暗号資産を担保することで価格を安定化させているステーブルコインです。代表的な暗号資産担保型のステーブルコインには、DAI(ダイ)やsUSD(SUSD)などがあります。
例えば、DAI(ダイ)は1DAI=1ドルと同じ価格を維持するように設計されていますが、その担保には150~200%程度の価格のイーサリアムなどを担保にしています。100%以上の暗号資産を担保にすることによって、暗号資産に大きな下落が起きても1DAI=1ドルを維持できるようにしています。
コモディティ型
コモディティ型のステーブルコインは、金や原油といった現物資産を担保にすることで価格を安定化しています。現物資産を担保にしているため、現物資産の価格変動に連動した価格で取引されます。
コモディティ型のステーブルコインには、Paxos Gold(PAXG)やジパングコイン(ZPG)などがあります。Paxos Gold(PAXG)やジパングコイン(ZPG)は現物の金価格と連動しているため、有事の際には価格が上昇する可能性があります。一方、長期保有する際は、金利の上昇やインフレによる実質的な資産の目減りには注意が必要です。
アルゴリズム型(無担保型)
アルゴリズム型(無担保型)は、裏付けとなる資産を持たないステーブルコインです。フラックス(FRAX)やTerraUSD(UST)などがあります。
暗号資産を発行するアルゴリズムによって、1ドルと同等の価値を維持(ペッグ)できるように、ステーブルコインの発行枚数を増やしたり、バーン(焼却)をしたりしています。
ただし、裏付けとなる資産を持たないため、信用不安によってペッグが外れてしまう可能性があります。実際、TerraUSD(UST)は、2022年5月に価格が維持できなくなり、99%以上の大暴落でほぼ無価値となっています。
<<あわせて読みたい>>
【ブロックチェーンの7つのメリット】デメリットもわかりやすく解説
ステーブルコインのメリット

ステーブルコインの主なメリットは以下の3つです。
- 価格が安定している
- 迅速かつ低コストな国際送金や決済が可能
- 資産運用によって利息が得られる
それぞれを解説します。
価格が安定している
1つ目のステーブルコインのメリットは、価格が安定していることです。
ステーブルコインは価格が安定するように設計された暗号資産であるため、ボラティリティ(価格変動)が小さいというメリットがあります。
価格が安定していることによって、ビットコインなどの暗号資産を、価格が安定したステーブルコインに退避することで、利益を確定したり、資産を暴落から守ったりする効果が期待できます。
ただし、ステーブルコインのペッグが機能不全になったり、担保としている資産の価値が下落した場合、ステーブルコインそのものの価格が暴落する可能性もあるため注意が必要です。
迅速かつ低コストな国際送金や決済が可能
2つ目のステーブルコインのメリットは、迅速かつ低コストな国際送金や決済が可能なことです。
法定通貨を使って国際的な送金や決済をする場合、相手方の通貨に両替をする際に手数料が発生したり、送金や決済に時間がかかったりします。その結果、手元に残る利益が減ってしまったり、ビジネスチャンスを逃してしまったりするリスクがあります。
一方、暗号資産の一種であるステーブルコインなら、ブロックチェーン技術を使うことで世界中の人々と低コストかつ迅速に取引ができます。
コストや時間のかかるSWIFTや銀行を経由せず、ステーブルコインを使って国際的な送金や決済を行えば、手元に残る利益を増やしたり、ビジネスチャンスをタイムリーに生かせる可能性が高まります。
資産運用によって利息が得られる
3つ目のステーブルコインのメリットは、資産運用によって利息が得られることです。
ブロックチェーン技術を使ったステーブルコインなら、手元の資産を運用することで利息や手数料などを稼げる可能性があります。CEX(中央集権型取引所)やDEX(分散型取引所)を使ってレンディングやステーキング、イールドファーミングなどを行えば、運用結果に応じた利息や手数料が得られる可能性があります。
<<あわせて読みたい>>
ブロックチェーンとは?分散型台帳の基礎や仕組み、セキュリティ、活用法を図解でわかりやすく解説!
ステーブルコインの注意点

安定的な価格で実用的なステーブルコインですが、取り扱いには注意が必要です。ステーブルコインの主な注意点は以下の3つです。
- 裏付けとなる資産を確認する
- 発行元の信頼性を確認する
- 政府による規制のリスクがある
それぞれを解説します。
裏付けとなる資産を確認する
1つ目のステーブルコインの注意点は、裏付けとなる資産を確認することです。
裏付けとなる資産を持たないアルゴリズム型(無担保型)のステーブルコインは、ペッグが機能不全となり価格が暴落する可能性があります。また、暗号資産担保型やコモディティ型のステーブルコインも、裏付けとなる資産の価格変動の影響を大きく受けます。
一方、比較的価格が安定しているのは法定通貨型のステーブルコインです。しかし、法定通貨型であっても、為替変動や金利、インフレなどの影響を受け、実質的な資産が目減りする可能性もあるため注意が必要です。
発行元の信頼性を確認する
2つ目のステーブルコインの注意点は、発行元の信頼性を確認することです。
ステーブルコインは、民間企業やDAO(分散型組織)などが発行元となります。政府が発行するドルや円などの法定通貨とは異なるため、発行元の信頼性をしっかりと確認することが大切です。発行元となる組織の経営状態や裏付け資産の保有状況、セキュリティ対策などはステーブルコインを扱う上で大切な情報となります。
政府による規制のリスクがある
3つ目のステーブルコインの注意点は、政府による規制のリスクがあることです。
分散型で非中央集権的なステーブルコインも存在しますが、暗号資産は各国政府の規制を受ける資産となります。そのため、ステーブルコインの取り扱いに関する規制や税制の影響には注意が必要です。
<<あわせて読みたい>>
【ブロックチェーンのセキュリティ】安全性や弱点、対策を徹底解説
ステーブルコインの将来性について
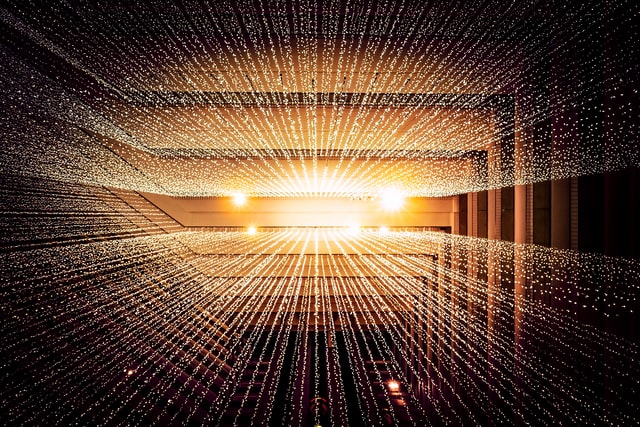
価格が安定していて実用性の高いステーブルコインは、今後もさまざまな場面での活用が期待されています。最新のステーブルコイン活用事例を紹介していきます。
日本円ステーブルコインのJPYCが累計発行額30億円を突破
2024年11月18日、日本円連動ステーブルコイン「JPYC」を取り扱うJPYC株式会社は、プリペイド型日本円ステーブルコイン「JPYC」の累計発行額が30億円を突破したことを発表しました。「JPYC」は現在、Ethereum、Polygon、Avalanche、Astar Network、Shiden Network、Gnosisの複数ブロックチェーンで利用が可能です。
JPYC株式会社では、個人間の送金やマイクロペイメント、企業間決済など、さまざまな分野や業界で幅広くステーブルコインが使われる未来を目指しています。実際、地方自治体のアイデア募集プラットフォームの報酬や、建設業界の福利厚生用サービスなど、スタートアップのイノベーションを加速させるための金融インフラとしての活用も始まっています。
JPYC株式会社は、ステーブルコインの特性である透明性や送金手数料の低減により、より効率的なデジタル金融イノベーションを促進しています。また、「JPYC」の発行額の増加や流動性の安定、取引コストの削減、エコシステムの拡大による取引の効率化などを目指しています。
参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000248.000054018.html
三井住友FGがステーブルコインの事業化に向けた共同検討に係る基本合意書を締結

2025年3月21日、三井住友フィナンシャルグループと三井住友銀行、TIS、Ava Labs、Fireblocksは、ステーブルコインの事業化に向けた共同検討の基本合意書を締結しました。
この基本合意では、金融機関や事業者間で行われる決済利用に耐えうるステーブルコインの具体的な要件定義を検討することになっています。また、実証実験を行うだけでなく、継続的な業務への活用を目指すものとなっています。
2023年6月1日に施行された改正資金決済法により、日本でもステーブルコインが電子決済手段として定義され、利用が正式に認められました。SMBCグループと、国内外でデジタルアセットをテーマとして先進的な取り組みを進めるTIS、Ava LabsおよびFireblocksが連携することで、国内における金融機能の効率化や高度化を後押しする狙いがあります。
参考:https://www.nikkei.com/article/DGXZRSP689223_S5A400C2000000
トランプ一族関与の仮想通貨企業がステーブルコインを発行
2025年3月25日、アメリカのトランプ大統領一族が関与する仮想通貨企業「ワールド・リバティ・ファイナンシャル(WLF)」は、米ドルに連動するステーブルコイン「USD1」を発行すると発表しました。
「USD1」は、米財務省証券や米ドル預金など現金に準じる資産を裏付けとし、1ドルと同等の価値を持つように設計されます。WLFは2024年10月に稼働を開始し、これまでにトークンの販売総額が5億5000万ドルを超え、8万5000人以上の投資家が集まっていると公表しています。
「USD1」についてWLFの共同創業者であるザック・ウィットコフ氏は「各国の政府系投資家や大手機関投資家が自信を持って投資戦略に組み込める、国境などの切れ目がない安全な国際取引のためのステーブルコインを提供する」と説明しています。
参考:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN25CCD0V20C25A3000000
米フィデリティが独自ステーブルコイン発行を計画
2025年3月26日、フィナンシャルタイムズは米資産運用大手フィデリティが独自ステーブルコインの発行を計画していると報じました。
すでにテストは最終段階にあるとのことですが、ステーブルコインの発行時期やブロックチェーンの選定、担保モデルについての詳細は現時点では公表されていません。
資産運用大手のフィデリティがステーブルコインを発行することにより、資産運用でのステーブルコインの活用が活発になっていくことが予想されます。
参考:https://news.yahoo.co.jp/articles/fa4401e3a645024ef5d09feda8ce5c99a6f8a5f3
リップル社、ステーブルコイン「RLUSD」のリップルペイメント導入を発表
2025年4月2日、国際送金に特化したリップル(XRP)を発行するリップル社は、同社が提供する国際送金ソリューション「リップルペイメント」でステーブルコイン「RLUSD」が利用できるようになったと発表しました。
RLUSDは2024年12月中旬にローンチされた米ドルステーブルコインで、複数の国際送金プロバイダーが利用しています。ローンチ以降100億ドル(約1.5兆円)規模の取引が行われていますが、リップルペイメントへの導入によって、RLUSDの企業向けの実用性と需要がさらに促進されると期待されています。
RLUSDは信頼性やコンプライアンスを重視し、企業が利用しやすくしてあるステーブルコインです。国際送金だけでなく、財務管理やDeFi(分散型金融)、仮想通貨事業、トークン化したRWA(現実資産)の取引などに企業が利用できるように開発が進められています。
参考:https://coinpost.jp/?p=606187
Tether社が米国市場専用のステーブルコインの提供を検討
2025年4月7日、米ドルに連動したステーブルコインであるUSDTを発行するTether社が、米国市場専用のステーブルコインの提供を検討していると、「フィナンシャルタイムズ」や「ザブロック」が報じました。
同メディアの取材に対し、テザー社のCEOであるパオロ・アルドイノ氏は、「アフリカなどの新興市場や金融包摂を支援するために開発したステーブルコインとは異なり、インフラ要件が大きく異なる大規模な規制対象機関のニーズを満たすように調整されることになるだろう」とコメントしています。
アメリカでは、トランプ大統領が8月までにステーブルコインに関する新たな規則を整備するよう求めていて、上院や下院でもステーブルコインに関する法案を審議中となっています。
参考:https://news.yahoo.co.jp/articles/47126bb52662d15dc59ab1ba02858003be705c67
まとめ ステーブルコインについて

今回は、暗号資産のステーブルコインについて解説しました。
価格が安定しているステーブルコインは、実用性が高いため今後さまざまな場面で広がっていくことでしょう。新たなステーブルコインの発行や活用事例も増えていくと予想されます。
今後も当メディアでは、ステーブルコインの最新動向を定期的にお届けしていきます。
株式会社リッカ
<<あわせて読みたい>>






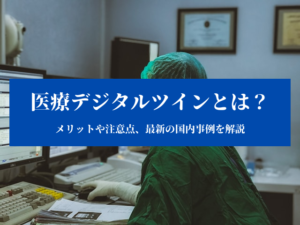

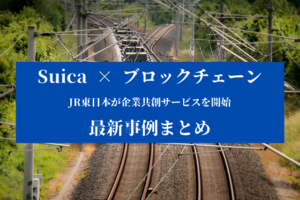
コメント