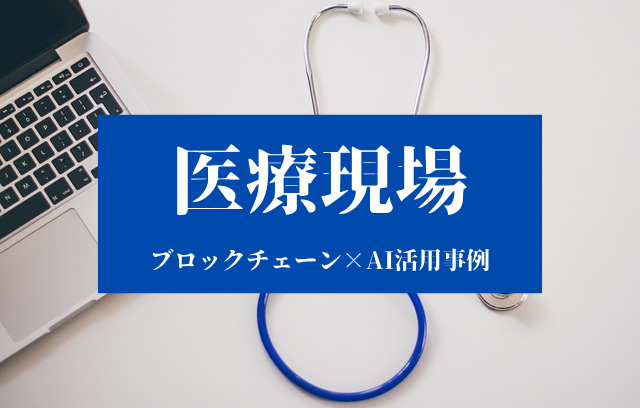
医療現場では個人の健康に関するデータを扱うため、情報セキュリティ対策が重要です。また、人手不足や業務量の増大により、さらなる業務効率化が求められています。
こうした医療現場での課題を解決し、人々が安心して暮らせる社会を作るために活用が期待される技術がブロックチェーンとAIです。
今回は、ブロックチェーンとAIが医療現場のどのような課題を解決し、どのような未来が期待できるのかについて解説します。
株式会社リッカ
<<あわせて読みたい>>
ブロックチェーンとは?分散型台帳の基礎や仕組み、セキュリティ、活用法を図解でわかりやすく解説!
医療現場における業務課題とは?

まずは医療現場においてどのような課題があるのかを確認していきましょう。医療現場における主な業務課題には以下の5つがあります。
- 医療情報を共有することの難しさ
- 慢性的な人手不足
- DX化の遅れによる非効率な業務の増大
- データセキュリティの確保やプライバシー保護の難しさ
- 患者や医療従事者の満足度の低下
それぞれを解説します。
医療情報を共有することの難しさ
1つ目の医療現場における業務課題は、医療情報を共有することの難しさです。
電子カルテや最新の医療機器の導入が進む医療現場ですが、基本的に医療情報は医療機関ごとに管理されています。
データ管理の方法やデータフォーマット、データの保存先などが医療機関によって異なるため、医療機関同士で医療情報を共有することは難しいです。また、個人情報保護の観点からも、患者が主体的に医療情報を提供する体制が整わない限り、医療機関の判断だけで患者に関する情報を共有することはできません。
医療情報が共有されないことで、新しい治療や創薬の開発に必要なデータが十分に得られない可能性があります。
慢性的な人手不足
2つ目の医療現場における業務課題は、慢性的な人手不足です。
医師や看護師などの医療従事者の人手不足は深刻さを増しています。過重な労働や過大な責任、高齢化による患者の増大、退職者の増加などが原因で、医療現場の疲弊は続いています。
さらなる高齢化によって人手不足に拍車がかかれば、過重な労働によってさらに退職者が増加するという負のスパイラルを止められなくなる可能性があります。
DX化の遅れによる非効率な業務の増大
3つ目の医療現場における業務課題は、DX化の遅れによる非効率な業務の増大です。
電子カルテや最新の医療機器の導入によってDX化が進む医療現場ですが、紙ベースで管理されている情報も多いため、DX化が遅れがちな分野となっています。患者や医療従事者の高齢化が進むことで、データ入力に手間や時間がかかってしまうことも大きな要因と考えられます。最新のシステムを導入するには大きなコストがかかりますが、紙ベースの管理を廃止できなければ十分な費用対効果が得られない可能性もあります。
DX化が遅れれば、情報の検索や共有に時間がかかり、医療現場の労働が過重になったり、患者の待ち時間が大幅に伸びたりする可能性があります。また、手書きによるミスや情報の紛失は、重大な医療事故の引き金になるリスクもあります。
データセキュリティの確保やプライバシー保護の難しさ
4つ目の医療現場における業務課題は、データセキュリティの確保やプライバシー保護の難しさです。
医療現場では、患者のカルテや病歴などの機微な個人情報を扱うため、データセキュリティの確保やプライバシー保護が大きな責務となっています。改ざんや紛失、漏えいなどからデータを守らなければいけないため、データセキュリティに費やす業務やコストが増大する傾向にあります。
医療情報を効率的に扱わなければ、医療現場の業務効率化は進みません。しかし、業務効率化を推進するためにデータを共有しやすくすれば、データの漏えいや改ざんのリスクが高まるというジレンマがあります。
患者や医療従事者の満足度の低下
5つ目の医療現場における業務課題は、患者や医療従事者の満足度の低下です。
人手不足やDX化の遅れ、業務量の増大などの結果、患者や医療従事者の満足度が低下する可能性があります。
患者においては、待合室で長時間待たされたり、十分な医療が受けられなくなったり、医療ミスの可能性が高まったりすることが考えられます。医療従事者においては、医療費削減の影響から十分な報酬が得られなくなったり、残業や夜勤が増えたり、過重な労働で体調を崩したりする可能性があります。
<<あわせて読みたい>>
【2023~2024年最新版】AI×ブロックチェーンの国内活用事例を紹介
医療現場でブロックチェーンを活用する5つのメリット

ブロックチェーンを活用することで、医療現場が抱えるいくつかの課題が解消できる可能性があります。ブロックチェーンを活用する主なメリットは以下の5つです。
- 患者が自身の医療情報を管理できる
- 医療情報を安全に共有できる
- 情報の透明性や信頼性が向上する
- データ活用によって新たな収益が得られる
- 新たな治療や創薬の開発が促進される
それぞれを解説します。
患者が自身の医療情報を管理できる
1つ目のブロックチェーン活用のメリットは、患者が自身の医療情報を管理できることです。
ブロックチェーンを活用すれば、患者の医療情報は患者自身が管理できるようになります。
従来、患者の医療情報は医療機関が保管していますが、本来この情報の多くの所有権は患者にあります。これまでは患者が医療情報を安全に保管する方法がなかったため、患者自身で医療情報を管理することができませんでした。
しかし、スマートフォンを始めとした電子デバイスの発達と、情報を改ざんできない形で安全に保存できるブロックチェーン技術の普及によって、患者が自身の医療情報を管理できるようになりつつあります。
患者が自身の医療情報を管理することで、医療機関ごとに分断されていた情報が集約され、治療の履歴やアレルギー情報などが一元管理できます。
<<あわせて読みたい>>
【Web3とは?】ブロックチェーンが何を実現するのか?徹底解説
医療情報を安全に共有できる
2つ目のブロックチェーン活用のメリットは、医療情報を安全に共有できることです。
ブロックチェーンは強固なセキュリティと分散型の管理によって、改ざんが極めて困難な状態で情報を保存できます。これにより大切な情報を共有しても第三者に改ざんされるリスクがほとんどないため、医療情報を安全に共有できます。
例えば、患者の病歴や治療歴を複数の医療機関で共有することで、より効果的な治療を選択できる可能性が高まります。また、副作用やアレルギーのリスクが共有できれば、医療事故が起きる可能性を低減する効果も期待できます。
<<あわせて読みたい>>
【ブロックチェーンの7つのメリット】デメリットもわかりやすく解説
情報の透明性や信頼性が向上する
3つ目のブロックチェーン活用のメリットは、情報の透明性や信頼性が向上することです。
ブロックチェーンに記録される情報は、複数の医療機関で確認ができる状態で保存されます。そのため、故意に誤った情報が保存されたり、何者かによって情報が改ざんされるリスクがほとんどありませんので、情報の透明性や信頼性が向上します。
情報の透明性や信頼性が向上することで、患者はより正しく効果的な治療を受けられる可能性が高まります。また、医療機関も正しい情報をもとに治療プランを検討できるため、より良い医療の提供が可能になります。
<<あわせて読みたい>>
【ブロックチェーンのセキュリティ】安全性や弱点、対策を徹底解説
データ活用によって新たな収益が得られる
4つ目のブロックチェーン活用のメリットは、データ活用によって新たな収益が得られることです。
ブロックチェーンによって医療情報の共有や活用が進めば、そのデータを活用した新たなビジネスモデルが構築できます。
例えば、患者が自身の医療情報を高度な医療機関やメディカル企業、研究機関に提供することで、謝礼として報酬を受け取ることもできるようになります。また、医療機関が持つ膨大な診療情報をメディカル企業や研究機関に提供することで、新たな収益の柱になる可能性を秘めています。
<<あわせて読みたい>>
スマートコントラクトとは?メリットや活用事例、注意点をわかりやすく解説
新たな治療や創薬の開発が促進される
5つ目のブロックチェーン活用のメリットは、新たな治療や創薬の開発が促進されることです。
ブロックチェーンを活用することで医療データの効率的な共有が可能になれば、新たな治療法や創薬の開発が加速する可能性があります。
新しい治療や創薬の開発には膨大なデータを必要としますが、ブロックチェーンによってデータ共有が活発になれば、より効率的な開発が可能となります。さらにAIを活用することで、医療DXはさらなる効率化を加速できる可能性があります。
<<あわせて読みたい>>
【医療×ブロックチェーン】DX化の課題やメリット、注意点、事例を解説
医療現場でAIを活用する3つのメリット

ブロックチェーンとともにAIを活用すれば、医療現場のさらなるDX化を促進できます。ここではAIを活用することで得られる主なメリットとして以下の3つを紹介します。
- 患者の待ち時間や院内の混雑を削減する
- より正確で迅速な診断を実現する
- データを分析して最適な治療プランを提案する
それぞれを解説します。
患者の待ち時間や院内の混雑を削減する
1つ目のAI活用のメリットは、患者の待ち時間や院内の混雑を削減することです。
例えば、医療機関の予約状況や診察の混み具合をAIがモニタリングし、医療スタッフの最適な配置やシフトを提案することが可能となります。また、予約時に空いている曜日や時間帯を提案したり、患者ごとに必要な案内をリアルタイムに表示することで院内の移動をスムーズにすることもできるようになります。
これにより患者の待ち時間が短縮できたり、院内の混雑が緩和することが期待できます。また、複数の科を受診する方や複数の検査を受ける方も、AIが最適な順番を提案することでより短い時間で受診や検査を終わらせることができ、患者の満足度を向上することが期待できます。
より正確で迅速な診断を実現する
2つ目のAI活用のメリットは、より正確で迅速な診断を実現することです。
医療情報をAIが分析することで、より正確で迅速な診断を可能にします。AIは膨大な画像データや検査データをもとに病気や怪我の症状を学習することができるので、小さな異変も見落とすことなく医師に知らせることができます。
これにより医師の過重な労働を削減しつつ、医療ミスを減らすことが可能となります。また、患者の異変をより早期に見つけることができるので、病気や怪我からの速やかな回復が期待できます。
データを分析して最適な治療プランを提案する
3つ目のAI活用のメリットは、データを分析して最適な治療プランを提案することです。
AIは患者の過去の診療データや最新の医療研究をもとに、最適な治療プランを医師に提案することができます。また、病気や怪我からの回復に必要な薬剤やリハビリ、食事メニューなども提案することができるので、患者の速やかな社会復帰をサポートできます。
提案した内容とその結果をAIにフィードバックすれば、さらにより良い治療プランを提案できるようになります。これにより経験の少ない医師でも最適な治療プランが組めるようになったり、医師不足に悩む医療機関の機能を維持できる可能性が高まります。
<<あわせて読みたい>>
【生成AIの活用】著作権などの注意点を解説(知らなかったでは済まない)
WEB3.0技術を活用した医療データ管理システム「ヘルスインタビュー」&「メディレコ」

大阪大学発の医療ベンチャー企業であるAIBTRUST株式会社は、WEB3.0技術を活用した医療データ管理システム「ヘルスインタビュー」と「メディレコ」をリリースしました。
参考:マイナンバー本人確認(デジタル認証アプリ)、WEB3.0を活用した医療情報返却システム「ヘルスインタビュー」「メディレコ」阪大発ベンチャーからリリース
ヘルスインタビューについて
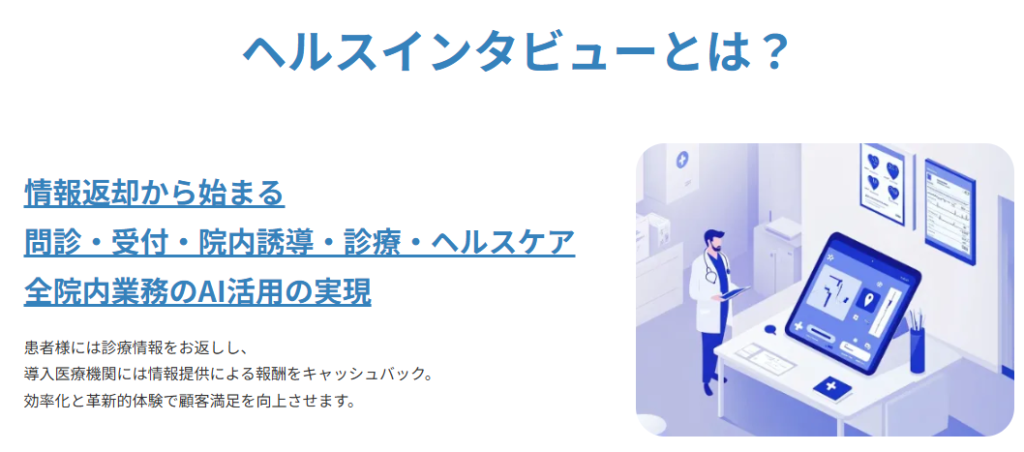
ヘルスインタビューは、医療機関が指定した範囲で患者本人に医療情報を容易に返却できるシステムです。また、医療機関同士で医療情報を安全に共有できるようになるため、より良い医療サービスの提供が可能になります。
メディレコについて
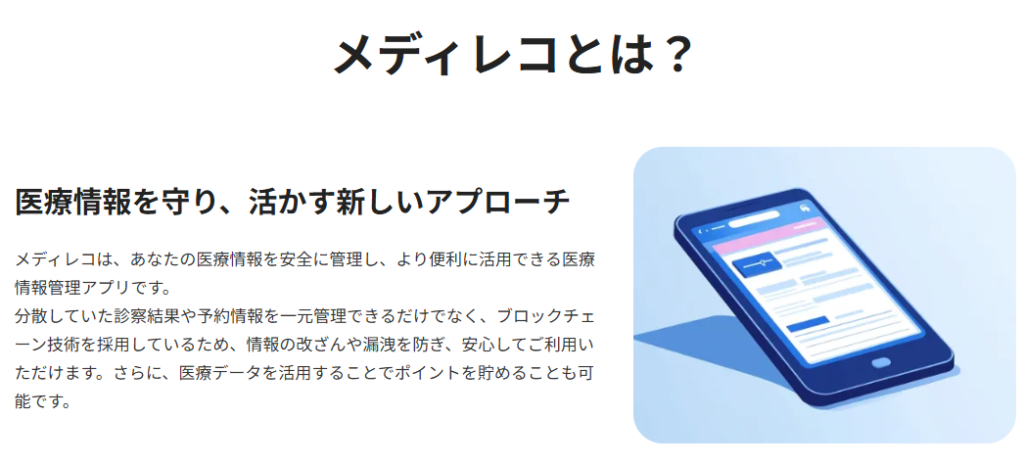
医療機関から返却された情報を患者自身が管理できるアプリです。分散していた診察結果や予約情報を一元管理できるようになります。また、メディレコの情報管理にはブロックチェーン技術を採用しているため、情報の改ざんや漏洩を防ぐことも可能です。
参考:AIBTRUST株式会社(大阪大学発ベンチャー)
まとめ 医療×ブロックチェーン×AIについて

今回は、医療現場の課題と、ブロックチェーンとAIを活用することのメリットについて解説しました。
DX化が遅れがちで人手不足も深刻な医療現場では、さまざまな業務課題があります。しかし、ブロックチェーンやAIを活用することで業務の効率化が進むだけでなく、コスト削減や患者の満足度向上、新しい治療や創薬の開発のチャンスも広がります。
将来性が期待されるブロックチェーンですが、ブロックチェーン開発には独特のノウハウや注意点があります。ブロックチェーンやスマートコントラクトを活用したシステム開発は、株式会社リッカにご相談ください。
株式会社リッカ
<<あわせて読みたい>>






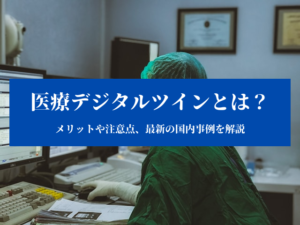

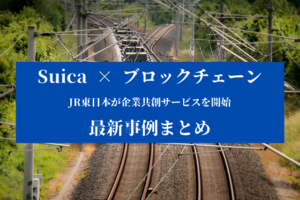
コメント